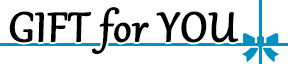各種の意味、違い
日本の風習として、季節や年度の変わり目にちょっとした贈り物を送るということがあります。
中でも代表的なのが「お歳暮」「お年賀」「寒中見舞い」で、いずれも年末年始の時期に送るものとして位置づけられています。
この3つは送る時期がほとんど同じくらいであることから、別々に送るべきか、それともまとめて送ってもよいのかとちょっと迷ってしまうでしょう。
まずこの3つの違いから説明をしていくと、お歳暮は年明け前の年末の時期に送るものとされています。
具体的には11月末から12月20日くらいまでの間に送るよいうもので、年が明けてしまったら「お歳暮」として送るのはやめておいた方がよいでしょう。
意味合いとしてはお世話になった一年のお礼というふうになっているので、年明けになってしまっては全く意味が異なってしまうことになります。
反対にお年賀は年明けをしてから、新しい一年もよろしくお願いしますという意味で送るものとなっています。
送る時期は「松の内」とされる門松を飾っておく期間までです。
この「松の内」は地域により期日に違いがあり、1月7日までとしているところもあれば1月15日までが含まれるというところがあります。
こちらも松の内を過ぎてしまうと贈答品としての意味が変わってしまいますので、必ず期日内に送るようにしましょう。
3つの中で最も基準が緩やかなのが寒中見舞いです。
寒中見舞いはその季節の寒さを気遣う意味で行う贈答品なので、あまり厳密に時期が決められているわけではありません。
一般的には1月頃~2月4日頃(立春)までとされており、贈答品としてだけでなくはがきなどの挨拶状として送ることもあります。
お歳暮やお年賀として送る予定だった品物が時期を失してしまった場合に「寒中見舞い」と名称を付け替えて送ることも可能です。
それぞれの御祝をするときの注意点
上記で説明したように、それぞれの贈答にはきちんと意味がありますので、もし送る予定であった品物が時期を過ぎてしまったら、必ず名称をつけかえるようにしましょう。
ただしお歳暮、お年賀、寒中見舞いのいずれも贈答品につける熨斗は紅白の蝶結びで共通していますので、表題となる部分の書き換えをすれば特に問題はありません。
品物そのものがお歳暮、お年賀、寒中見舞いで区別されることはありませんので、お歳暮用に買った贈答品を再び買い換えるということはしなくても良いでしょう。
年賀を送る時期内であっても、先方に一年以内の不幸があり喪中という場合には「年賀」という名称を用いないようにします。
その場合は「寒中見舞い」という名称にして同じ品物を送れば、特に不義理というふうに思われることはありません。